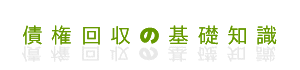少額訴訟の利用方法・利用条件
少額訴訟の利用条件
少額訴訟を利用するにはいくつか条件があります。
条件
・60万円以下の金銭支払い請求のみ
・一年間に同じ裁判所で少額訴訟を利用できる回数は10回まで
・原則、相手住所地を管轄する簡易裁判所で少額訴訟が行われる
・相手の住所が不明な場合は起こすことができない
・判決に不服があっても、控訴はできない
60万円以下の金銭支払い請求のみ
60万円を超える場合は少額訴訟ではなく、他の手段を考えるか、どうしても少額訴訟にしたい場合は何度かに分けて提起しなければなりません。この60万円というのは利息等含まない額です。
利息等を含まないとは、例えば60万円を相手に貸している場合に利息や遅延損害金を含めると65万円になった場合でも、元々、貸したお金(元本)は60万円ですので、少額訴訟を利用することができます。
また、金銭の支払いを請求するのみに限られ、具体的には以下のようなものが上げられます。
・貸したお金を返してもらいたい・敷金を返してもらいたい
・商品代金を払ってくれない・給料を払ってくれない
一年間に同じ裁判所で少額訴訟を利用できる回数は10回まで
一般の方でしたら何度も利用することはないと思いますが、業者対策として一年間に同じ裁判所で少額訴訟を利用できる回数は10回までと決まっています。
訴状を書く際にも回数を書かなければならず、備え付けの訴状用紙にも記入欄があります。
原則、相手住所地を管轄する簡易裁判所で少額訴訟が行われる
訴える相手側が法人である場合では会社の本店所在地を管轄する簡易裁判所となります。相手の住所地、本店所在地の管轄する簡易裁判所で少額訴訟が行われることを原則としているので、遠方の場合は、そこまでに行く手間や費用がかかってしまいます。
例外
・あらかじめ双方の話し合いにより、争いになった場合に裁判所を決めているとき
・不法行為が発生した場所
・手形や小切手の支払地
・義務履行地
判決に不服があっても、控訴はできない
少額訴訟は簡易裁判所で行われますが、判決に不服があっても、上級の裁判所に再審査を求めることはできません。
ただし、少額訴訟を起こした簡易裁判所に対し、異議を申し立てることはできます。その場合は、訴訟が終結前の状態に戻り、通常訴訟の手続きにより行われることとなります。
少額訴訟メニュー
貸したお金が返ってこない、敷金が返還されない/お金に関する悩み解決サイト少額訴訟は通常の訴訟に比べ費用を安抑えることができます。